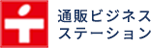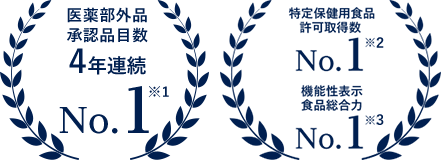青汁 OEM商品開発-市場シェア拡大!消費者ニーズに応える差別化戦略とは?
- 健康食品・サプリ記事(111)
- 商品開発(56)
- 原料・成分(42)
- 2025.09.19

この記事で分かること
- 青汁市場の内訳・最新動向と、競争激化の背景(紅麹問題や物価高など)の捉え方
- コロナ禍以降の消費者ニーズ変化(味重視型から機能性重視型)と、伸び筋カテゴリのヒント
- OEMで差別化する具体策(味のバリエーション、原料選定、製造方法による品質・風味設計、機能性表示食品化の活用)
- 年代・性別の嗜好、パッケージデザイン、SNSでの拡散を踏まえた“売れる青汁”の設計ポイント
健康食品市場で定番の青汁(グリーンスムージー含む)は、市場規模が約1,000億円に達しています。しかし、その競争は激化しており、各社は市場で勝ち残るためにさまざまな工夫を凝らしています。特に、コロナ禍を経て健康志向が高まったことで、「おいしく手軽に健康を」という消費者ニーズへと大きく変化しました。
本記事では、青汁の多様化する消費者ニーズを分析し、OEMを活用した商品開発でどのように差別化を図るかについて、そのヒントをお届けします。
- 目次
- 1.青汁「1,000億円市場」の内訳と、最新動向
- 1-1.消費者ニーズの変化:味重視型から機能性重視型へ
- 1-2.健康志向・安全安心志向と青汁需要
- 1-3.競合製品分析:トップブランドの戦略と成功要因
- 2.OEMを活用した青汁商品の差別化戦略とは?
- 2-1.味のバリエーションによる差別化
- 2-2.原料による差別化
- 2-3.製造方法の違いが生み出す品質・風味の差別化
- 2-4.機能性表示食品としての差別化(大手メーカーの事例)
- 3.消費者分析:嗜好・パッケージデザイン・SNS
- 3-1.年代別・性別の青汁の好みの傾向
- 3-2.パッケージデザインと商品訴求力
- 3-3.SNS「映え」する青汁とは?
- 4.まとめ
青汁「1,000億円市場」の内訳と、最新動向
青汁市場の現状をより深く理解するため、まずは市場規模の内訳からユーザーニーズの変化、健康意識の高まりとの関連、そして市場をリードする各ブランドの戦略までを見ていきましょう。
健康産業新聞社の調査によれば、2024年通期の青汁市場は1,003億円規模に達しました。しかし、トレンドとしては減少傾向です。この背景には、2024年3月のいわゆる紅麹問題で機能性表示食品や健康食品に対するネガティブな報道が相次いだことや、食品・日用品価格の高騰などがあります。
2022年のデータによると、原料別のシェアは以下の通りです。
- 大麦若葉:46%
- ユーグレナ(ミドリムシ):13%
- クロレラ:11%
- ケール:7%
市場動向調査では、青汁製品の販売状況について「縮小」との回答が約60%を占め、市場の飽和感を指摘する声が目立ちます。しかし、機能性表示食品として届出された青汁製品は比較的好調。明確な「目的」を訴求する製品であれば、まだチャンスはありそうです。
このことは、青汁のOEM商品開発を狙う健康食品メーカー・ブランドオーナーにとって、新たな差別化戦略の必要性を示唆しています。市場でのシェアを獲得するためには今後ますます、機能性に特化する、特定ターゲット層に絞るといった明確なテーマを持つ商品設計および開発が、不可欠になるでしょう。
消費者ニーズの変化:味重視型から機能性重視型へ
かつて、青汁といえば「まずい もう一杯」のCMに代表される「健康のために我慢して飲むもの」というイメージでした。しかし、現在は大きく変化しています。
2020年6月のデータによると「コロナ禍が健康意識に影響を与えた」人は75.3%。特に20代~30代で顕著です。また、88.5%が「免疫力の重要性」を再認識し、95.3%が「健康維持には免疫力対策が不可欠」と回答しています。
この健康志向の高まりから、青汁は「なんとなく体に良い」「野菜の代替品」ではなく、「明確な機能性」を持った商品開発が求められています。
特に注目すべきは、免疫機能向上や腸内環境改善に働きかける「乳酸菌配合青汁」の人気です。腸内フローラを整える「腸活」への関心が高まり、「整腸作用」と「免疫作用」の両方を訴求できる青汁と乳酸菌の組み合わせが評価されています。
さらに、消費者は今や「美味しく機能性を摂取する」商品を求めています。今後はさらに、この消費者の意識およびニーズの変化に対応した商品開発が、市場シェア拡大の鍵となるでしょう。
| 消費者意識の変化 | 青汁製品開発の方向性 |
|---|---|
| 健康・免疫意識の高まり | 機能性を重視した製品設計 |
| 「腸活」への関心増加 | 乳酸菌など腸内環境改善成分の配合 |
| 我慢→楽しむ健康志向 | 美味しさと機能性の両立 |
健康志向・安全安心志向と青汁需要
新型コロナウイルス感染拡大による日本人の健康意識の転換を表わすデータは、他にもあります。
日本政策金融公庫「2024年消費者動向調査」では、食に関する「健康志向」が45.7%と連続で上昇。特に20代と40代で顕著な増加が見られます。また、コロナ禍で「免疫力の重要性を再認識した」人は88.5%に上ります。前述の乳酸菌配合の青汁商品が好調なのは、腸内環境を改善する「腸活」を通じた免疫機能向上への、期待の表れといえます。
また、「月に1回以上有機農産物を購入している」人が56.9%である点も注目です。青汁のOEM商品開発においても、有機JAS認証原料の使用が、差別化ポイントになりつつあります。
これらのことからも、消費者の「安全・安心」志向を捉えることが、今後の市場シェア拡大のポイントとなるでしょう。
競合製品分析:トップブランドの戦略と成功要因
通信販売の青汁市場においては、まずキューサイが「栄養素」を訴求して青汁市場を創出。続いてアサヒ緑健が「飲みやすさ」で参入し、高いシェアを獲得しました。その後、青汁市場は成熟と共に機能性による差別化が進みました。
トクホ(特定保健用食品)の青汁で「お腹の調子を整える」などの機能性を訴求した商品が登場。世田谷自然食品はトクホではなく、「乳酸菌」を配合した機能性で差別化に成功しました。新日本製薬は「血中中性脂肪・体脂肪・血圧」ケアを目的とする機能性表示食品で差別化し、EC販路も活用して、売上を拡大しています。
店頭流通では、伊藤園が「ごくごく飲める」という飲みやすい青汁でシェアを獲得。日本薬健も「金の青汁」という国産の大麦若葉を主原料とした青汁で、特にドラッグストアで広く支持されています。市場の約8~9割は「粉末タイプ」ですが、伊藤園は「ドリンクタイプ」の利便性を訴求しています。
| 成功企業 | 戦略・差別化ポイント |
|---|---|
| キューサイ | 栄養素の訴求 |
| アサヒ緑健 | 飲みやすさの訴求 |
| 世田谷自然食品 | 乳酸菌配合でシニア層に訴求 |
| 新日本製薬 | 機能性表示食品としての差別化 |
| 伊藤園 | ドリンクタイプの利便性 |
OEMを活用した青汁商品の差別化戦略とは?
ここからはOEMを活用した青汁商品開発・差別化戦略の具体的なアプローチとして、味のバリエーションの工夫、原料選定、品質向上、そして機能性表示食品としての展開などを解説します。
1. 味のバリエーションによる差別化
青汁市場において「味のバリエーション」は、差別化のための重要なアプローチ方法の一つです。
消費者調査データによれば、青汁の嗜好性や好まれるフレーバーは、年代・性別によって明確な違いが見られます。
- 20代〜30代の若年層:「フルーツ青汁」が人気、フルーティーな味わいが支持される。特に女性は柑橘系やりんご風味を好む傾向。
- 40代〜50代の中高年層:大麦若葉やケールなど主原料の風味を活かした青汁を選ぶ傾向が強い。
- 60代以上のシニア層:性別に関わらず「飲みやすさ」優先。ほのかな甘みと抹茶風味の組み合わせが特に人気。
こうした消費者嗜好の多様化に対応できるOEMメーカーを委託先に選ぶことで、フレーバー設計の自由度が高まります。
キューサイでは期間限定のポップアップストアで従来の青汁イメージと異なる「ケールチーズティー」「ケールジンジャー」といった斬新なフレーバーの青汁ドリンクを提供するなど、各社とも消費者ニーズを探るさまざまなマーケティング活動を行っています。
消費者が青汁を選ぶ際、「味」は「コスト」と並ぶ重要な要素です。例えばプロテイン製品では、ココア味やチョコ味が定番ですが、さまざまな味のバリエーションを登場させて飽きられないようにしています。青汁においても、味のバリエーション開発は、差別化ポイント。味の開発には、経験・ノウハウとスキルが必要となるため、OEMメーカー選びは慎重に行いましょう。
2. 原料による差別化
青汁商品の差別化を図る上で、原料の選定は非常に重要です。代表的な青汁原料は大麦若葉、ケールのほか、明日葉、ユーグレナ(ミドリムシ)、甘藷若葉などがあり、それぞれ栄養・機能面と味に特徴があります。ここでは主要な3つの原料を簡単に紹介します。
大麦若葉:
大麦若葉を粉砕した大麦若葉末は、クセがなく飲みやすいことが特徴。食物繊維がキャベツの約20倍と豊富です。青汁初心者や継続的な摂取を重視する顧客向けの青汁商品に、「続けやすい」点で適しています。
ケール:
キャベツやブロッコリーの原種で「野菜の王様」と呼ばれるスーパーフードです。ビタミンAがかぼちゃの約2倍、カルシウムが牛乳の約2倍と栄養価が非常に高いのが特徴。加えて、ケール由来のカルシウムは吸収が良いといわれています。味は独特の苦み・青臭さがありますが、栄養を感じる味とも言えます。最近では苦みの少ない品種もあります。
明日葉:
特有のポリフェノールであるカルコンを含むのが特徴。「今日摘んでも明日には葉が出る」名前の由来からも分かる通り、生命力が強い植物です。抗酸化作用が高く、滋養強壮効果が期待できるほか、食物繊維も多く含み、美容目的の青汁商品にも適しています。味は、青臭さや苦みは少なく、比較的飲みやすい青汁の原料として人気があります。
青汁のOEM商品開発では、飲みやすさを重視するなら大麦若葉、栄養価を前面に出すならケール、特定の機能性を強調するなら明日葉や他の青汁原料というように、ターゲット層と訴求ポイントに合わせた原料の選択が重要です。
3. 製造方法の違いが生み出す品質・風味の差別化
青汁の品質と風味を左右するのが、青汁原料の製造方法です。代表的な製法には生搾り製法と乾燥粉砕製法があり、それぞれ以下の特徴があります。
生搾り製法:
ケールなどの原料を収穫後すぐに搾汁する方法。鮮度と栄養価の保持に優れています。搾る力を調節することで苦味やえぐみを抑制する方法や、コールドプレス製法と呼ばれる、低温でゆっくりと圧搾して抽出することで摩擦熱を抑える方法なども開発されています。
乾燥粉砕製法:
原料を乾燥させてから粉末化する方法。保存性に優れる反面、大麦若葉のような繊維が多い原料においては粉っぽさが課題と言われてきました。しかし、東洋新薬では粉っぽさを感じない程度まで加工する「微粉砕製法」により、のど越しのよい大麦若葉青汁が開発可能です。
4. 機能性表示食品としての差別化(大手メーカーの事例)
機能性表示食品制度を活用した青汁商品開発は、市場での差別化や競争優位性の確立に有効。市場調査データにおいても機能性表示食品の青汁を選ぶ消費者が増え、一般健康食品から機能性表示食品にリニューアルする商品も出てきています。
アサヒグループ食品:
「からだ想いの青汁」を「L-92乳酸菌」を配合した機能性表示食品としてリニューアル発売しました。「健康な人の免疫機能の維持に役立つ」との訴求を打ち出しています。
伊藤園:
「毎日1杯の青汁 無糖」を機能性表示食品としてリニューアル。難消化性デキストリン配合により「食後の血糖値や中性脂肪の上昇を抑制する」機能を明確に訴求しました。リニューアル前の時点で前年比50%の成長を達成していた青汁商品ですが、さらなる成長を目指し機能性表示食品にリニューアルされました。
ファンケル:
2022年2月に発売した「野菜と乳酸菌とビフィズス菌がとれる青汁」を、同年10月に機能性表示食品にリニューアル。機能性表示食品となったことで「腸内環境を良好にし、腸の調子を整える」機能性をパッケージに明確に表記可能となり、訴求力が高まりました。
新日本製薬:
「Wの健康青汁」は、最初から機能性表示食品として開発された青汁商品。「機能性表示食品青汁国内売上No.1」(TPCマーケティングリサーチ調べ2023年メーカー出荷)を謳っています。肥満気味の方の体重・体脂肪の減少を助ける機能と、高めの血圧を下げる機能というダブルの機能を訴求して、市場に受け入れられています。
このように明確な機能性を表示することで、単なる「栄養補給」から一歩進んだ価値訴求が実現します。
消費者分析:嗜好・パッケージデザイン・SNS

続いて、消費者の多様なニーズに応えるため、年齢や性別による嗜好の違い、パッケージデザインの訴求力、SNS時代の消費者行動の変化を分析してみましょう。
年代別・性別の青汁の好みの傾向
消費者調査データからは、青汁の嗜好性、好まれるフレーバーの明確な年代・性別による違いが見て取れます。
- 20代〜30代の若年層:フルーティーな味わいが支持されています。特に女性は、柑橘系やりんご風味を好む傾向にあります。
- 40代〜50代の中高年層: 大麦若葉やケールなど主原料の風味を活かした青汁を選ぶ傾向が強いといえます。
- 60代以上のシニア層: 性別に関わらず「飲みやすさ」が優先。ほのかな甘みと抹茶風味の組み合わせが、この年代では特に人気を集めています。
パッケージデザインと商品訴求力
青汁商品の購買意欲を左右するパッケージデザイン。例えば、美容に関心のある女性ターゲットの青汁商品、キューサイの「ケールdeキレイ」は、カラフルで華やかなデザインのパッケージを採用するなど、「おしゃれ」「高級感」は価格プレミアムを生み出す要因となります。青汁のOEM商品開発において、ターゲット層の価値観に合わせたデザイン設計は、差別化のためますます重要度を増すでしょう。
SNS「映え」する青汁とは?
SNS時代の今、青汁商品も見た目の美しさと話題性が拡散度合いに繋がり、売上を左右します。
キューサイが展開する「表参道ポップアップストア」では、カラフルなドリンクの提供、フォトスポット設置やストローカスタマイズなど、SNS投稿を促す工夫が随所に見られました。
青汁商品のOEM開発でも、SNSでの消費行動を考慮した商品設計を取り入れる必要があります。SNSは「体験」「共有」がキーワード。開発コストや技術的なハードルはありますが、例えばパッケージの開封過程を楽しめる仕掛け、飲むたびに異なる見た目が楽しめる層状ドリンクなど、消費者が思わず写真を撮って共有したくなるような工夫ができると、若年層への認知にはプラスとなるでしょう。
まとめ
いかがでしょうか。健康志向の高まりと共に、青汁市場は競争が激化しています。その中で市場を勝ち抜くためには、多様な消費者ニーズに対応した明確な差別化戦略が不可欠です。
機能性表示食品として「明確な機能性」を訴求する製品は好調であり、免疫機能向上や腸内環境改善を目的とした乳酸菌配合の青汁も人気を集めています。また、消費者ニーズの変化に合わせて、美味しさを追求した味のバリエーション、ターゲット層に合わせた原料選定、そして品質や風味を高める製造方法も重要な差別化のポイントです。
東洋新薬は、長年の経験と技術力に基づいたODM/OEM事業で、お客様の課題解決をサポートします。消費者ニーズを捉えた独自の青汁商品開発をお考えの健康食品メーカー・ブランドオーナーの皆さま、ぜひお気軽にお問い合わせください。

東洋新薬は健康食品・化粧品業界を陰で支えるODEM(ODM&OEM)メーカーとして、世界の人々の『健康と美』への期待に『価値』で応えていくことをミッションとしています。 本サイトでは通販ビジネスにかかわるすべての皆様に様々な情報をお届けしています。
関連情報

青汁の原材料「大麦若葉」の栄養成分や機能、効果についてご紹介すると共に、いかに差別化商品を生み出すかなどの商品開発ヒントとなる情報もまとめています。
関連記事
-
1

- 機能性関与成分とは?概要から分析方法まで解説
- 健康食品・サプリ記事
- 商品開発
-
2

- オーラルケアOEM特集!企画~製造~開発のヒントを一挙ご紹介
- 健康食品・サプリ記事
- 商品開発
-
3

- 注目の高まる女性向けプロテイン ~商品開発のヒント
- 健康食品・サプリ記事
- 商品開発
-
4

- 青汁OEM販売までの4ステップ~費用やロット数にも注意!
- 健康食品・サプリ記事
- 商品開発
-
5

- 機能性表示食品の研究レビューを解説。届出資料作成上のポイント
- 健康食品・サプリ記事
- 商品開発
-

- 製剤技術「イージーパウダー®」のご紹介
-

- スタートアップ企業必見!20代~40代向け 青汁 OEM商品開発の成功ポイント
-
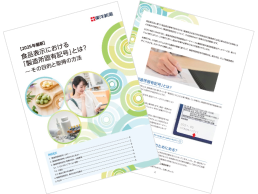
- 【2025年最新】食品表示における「製造所固有記号」とは?― その目的と取得の方法
-

- 開発実績多数あり!「免疫ケアタブレットOEM CRL1505乳酸菌」の商品カタログ資料
-

- Wellness Daily News 健康食品 Inside Out 大麦若葉青汁ができるまで
-

- Wellness Daily News サプリ製造の現場から 東洋新薬品質保証編/工場内部へ
-
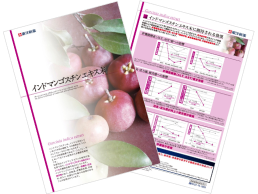
- インドマンゴスチンエキス末のご紹介
-
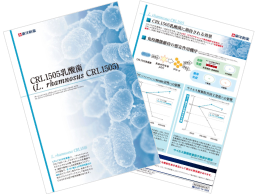
- CRL1505乳酸菌のご紹介
-

- 開発実績多数あり!「インドマンゴスチン脂肪・BMIケアタブレットOEM」の商品カタログ資料
-

- 開発実績多数あり!「溶けやすいプロテイン粉末飲料OEMイージーパウダー®」の商品カタログ資料
-

- 商品開発担当者向け 機能性表示食品届出の「3つの壁」~事例から見たその回避術
-

- 開発実績多数あり!「飲みこみやすいイージータブ® ブラックジンジャーサプリメント」の商品カタログ資料
-

- 健食・化粧品商品開発専用スペース「クイックラボ渋谷(QLS)」のご案内
-
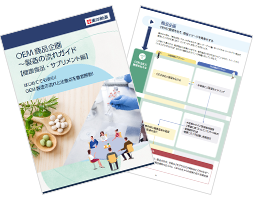
- OEM 商品企画~製造の流れガイド~【健康食品・サプリメント編】
-

- 黒ショウガエキス末のご紹介
-

- 「売れる青汁」は主原料に注目!差別化商品を生み出す5つのポイント
-
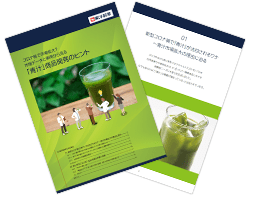
- コロナ禍で市場拡大? 市場データと事例から見る「青汁」商品開発のヒント
-

- 機能性表示食品 免疫ケアタブレットCRL1505乳酸菌
-

- 機能性表示食品 脂肪・BMIケアタブレット
-

- 溶けやすいプロテイン粉末飲料
-

- イージータブサプリメント
-

- オーラルケアタブレット
-

- 特保の青汁
-

- 機能性表示 ダイエットサプリ