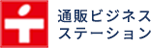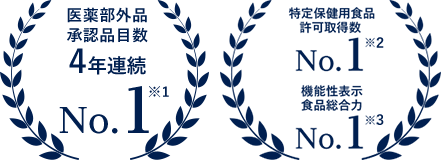サプリメント・健康食品の販売で注意すべき3つの法律
- 健康食品・サプリ記事(86)
- 関連法規(6)
- 2020.10.29

サプリメントや健康食品を販売する際には、さまざまな法律が関わります。知らぬ間に法律違反を犯さないように、これらを正しく理解することが必要になります。
今回は、サプリメント・健康食品の広告表示や販売方法において特に気を付けるべき以下3つの法規について解説します。
1. 景品表示法
2. 薬機法
3. 特定商取引法
サプリメント・健康食品販売に許可は必要?
結論、サプリメント・健康食品を販売する際に、必ずしも許可が必要とは限りません。しかし基本的には、サプリメント・健康食品は「食品」として扱われるため、食品衛生法に基づいた営業許可や責任者の資格等が必要になる場合が多いです。
海外からサプリメントを輸入して販売したい場合などは、厚生労働省の許可が必要になるなどの注意が必要になります。
またサプリメントの形状や、形態、、使用する成分によって関連する法律は変わってきますが、主に、食品衛生法、食品表示法、健康増進法、景品表示法、特定商取引法、薬機法などが関わってきます。
今回はその中でも特に注意が必要な3つに絞って解説していきます。
サプリメント・健康食品販売で気を付けたい法律① ~景品表示法とは~

正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」。「景品表示法」や「景表法」などと呼ばれます。
この法律では商品やサービスの品質、内容、価格、取引条件等について、「実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させる表示」を禁止しています。
例えば、次のような表示はできません。
・そのような事実はないのに「食事制限をしなくてもやせる!」と表示する
・外国産原料を使用しているのに「国産使用」と表示する
・通常価格での販売の実績がないのに「通常価格から50%オフ!」
・実際には申込者全員に同じ価格で販売しているのに「100人限定で割引」と表示
また、景品表示法は、過大な景品を提供することを禁止しており、景品の最高額、総額等を規制しています。例えば、購入すれば必ずもらえる景品の場合、景品の最高額は次のように決められています。
・取引金額が1,000円未満の場合:200円
・取引金額が1,000円以上の場合:取引金額の20%
商品に「おまけ」をつける、といった際には、これらの上限を守る必要があります。
違反行為を行った場合、行政より「措置命令」が出されます。また売上額に応じた課徴金の納付も命令されます。
>詳細は消費者庁のサイトを参照ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/
サプリメント・健康食品販売で気を付けたい法律② ~薬機法とは~
正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」。「医薬品医療機器等法」「薬機法」などと呼ばれます。その名のとおり、医薬品や医療機器などについて、品質、有効性、安全性を確保する他、危害の発生や拡大の防止などの目的で、製造、表示、販売、流通、広告などについて定めた法律です。
薬機法では承認を受けていない医薬品の販売や広告を禁止しています。健康食品は医薬品ではありませんが、医薬品であるかのような表現をした場合は医薬品とみなされ、承認を受けていない医薬品の広告を行ったとして薬機法違反になります。
例えば、健康食品に次のような表示はできません。
<医薬品的な効能効果の表現>
・病気の治療・予防を目的とする表現
例:「ガンに効く」「高血圧の改善」「動脈硬化を防ぐ」「便秘が治る」等
・体の機能の一般的増強、増進を目的とする表現
例:「疲労回復」「体力増強」「老化防止」「新陳代謝向上」「肝機能向上」「成長促進」
・その他医薬品的な効能効果を暗示する表現
・名称やキャッチフレーズで暗示するもの
例:「延命〇〇」「不老長寿」「漢方秘宝」「皇漢処方」
・含有成分の説明により暗示するもの
例:「血液をサラサラにすると言われている〇〇を主原料にして…」
・製法の説明により暗示するもの
例:「漢方薬の原料でもある〇〇を原料とし…」
・原料の由来の説明により暗示するもの
例:「古くから肝臓の薬として愛用されてきた〇〇は…」
・新聞、雑誌等の記事、医師・学者等の談話、学説、経験談などで暗示するもの
例:「〇〇は日本××学会でガンに効果があることが発表されました。」
・好転反応があることを表示するもの
例:「摂取後一時的に下痢などの反応が出ることがありますが、体内浄化のための初期症状ですので、そのまま摂取を続けてください」
・「ききめ」「効果」などの表現
例:即効性はありませんが、じわじわと効果が表れます。
<医薬品的な用法用量の表現>
服用時期・服用間隔・服用量を定める表現や、医薬品固有の服用方法の表現は、医薬品的用法用量の表現とみなされ、表示できません。
例:「1日2粒」「食前食後に」「お休み前に」「食間に」
「肝臓に悪い方は1日6粒、健康維持目的の方は1日3粒」
「オブラートに包んでお飲みください」
※食品であることを明示した上で摂取量の目安量を示すことは認められていますので、「1日〇粒を目安に摂取ください」「1日摂取目安量〇粒」などの表示は可能です。
薬機法に違反する行為を行った場合、罰金・懲役などの刑事罰が課されることもあります。
>健康食品と薬機法の関連については、東京都福祉保健局のサイトが参考になります。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/index.html
サプリメント・健康食品販売で気を付けたい法律③ ~特定商取引法とは~

正式名称は「特定商取引に関する法律」。「特商法」「特定商取引法」などと呼ばれます。消費者トラブルを生じやすい販売方法を対象にして、事業者が守るべきルールとクーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。
通信販売、訪問販売、連鎖販売取引(マルチレベルマーケティング)などが対象になります。
特定商取引法で例えば次のようなことを規制しています。
<訪問販売の場合>
勧誘に先立って事業者の氏名・勧誘目的であること・商品の種類を明示することや、消費者が断った場合にそのまま勧誘を継続することの禁止、契約が結ばれた場合には決められた事項を記載した書面を作成すること、事実と異なる説明や告げるべき事実を告げないことの禁止、等が定められています。
<通信販売の場合>
販売価格や事業者の名前など広告記載事項の義務付け、事実と相違する表示などの虚偽誇大広告の禁止、あらかじめ承諾の無い者への電子メール・FAX広告の送信の禁止、消費者の意に反して申し込みさせる行為の禁止、等が定められています。
<連鎖販売取引の場合>
勧誘を行う際には統括者や勧誘者の氏名を消費者に伝えること、契約締結についての勧誘目的であることを告げること、商品の種類を告げること、契約時の書面の交付義務、事実と異なる説明や告げるべき事実を告げないことの禁止、等が定められています。
特定商取引法に違反する行為を行った場合、業務改善指示や業務停止命令が出されます。
>詳細は消費者庁のサイト「特定商取引法ガイド」を参照ください。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/
まとめ

以上のように、健康食品の販売にはさまざまな法律が関係します。これらの法律に違反し行政処分や刑事罰を受けると、社会の信頼を損ね、会社の運営にも大きな悪影響を及ぼすことになりかねません。そうならないようにするためにも、関連法規について理解を深めていきましょう。

東洋新薬は健康食品・化粧品業界を陰で支えるODEM(ODM&OEM)メーカーとして、世界の人々の『健康と美』への期待に『価値』で応えていくことをミッションとしています。 本サイトでは通販ビジネスにかかわるすべての皆様に様々な情報をお届けしています。
関連情報
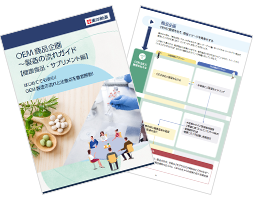
機能性表示食品の商品開発を例に、健康食品・サプリメントのOEM製造の流れを細かくまとめた資料です。お客様側とOEM側のそれぞれの対応や注意点などをご紹介します。
-
1

- 食薬区分とは?食薬区分改正で注目の成分もご紹介!
- 健康食品・サプリ記事
- 関連法規
-
2

- 「保健機能食品制度」とは?
- 健康食品・サプリ記事
- 関連法規
-
3

- サプリメント・健康食品の販売で注意すべき3つの法律
- 健康食品・サプリ記事
- 関連法規
-
4

- 健康食品と栄養成分表示について。消費者の関心が高い成分とは?
- 健康食品・サプリ記事
- 関連法規
-
5
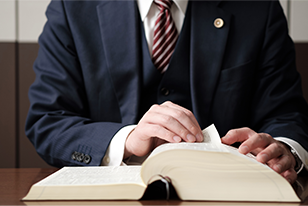
- 消費者庁 機能性表示食品 事後チェック指針 とは?
- 健康食品・サプリ記事
- 関連法規
-

- 健食・化粧品商品開発専用スペース「クイックラボ渋谷(QLS)」のご案内
-
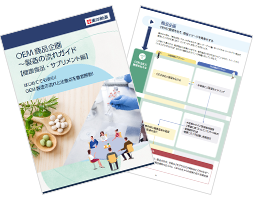
- OEM 商品企画~製造の流れガイド~【健康食品・サプリメント編】
-

- 黒ショウガエキス末のご紹介
-
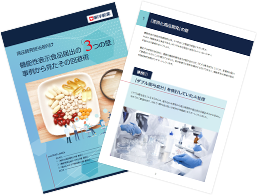
- 商品開発担当者向け 機能性表示食品届出の「3つの壁」~事例から見たその回避術
-

- 「売れる青汁」は主原料に注目!差別化商品を生み出す5つのポイント
-
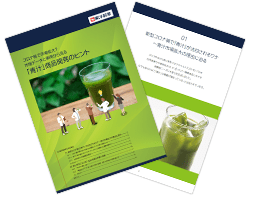
- コロナ禍で市場拡大? 市場データと事例から見る「青汁」商品開発のヒント